2025.07.24
【焼酎入門】芋・麦の違いとは?はじめてでも楽しめるおすすめの飲み方
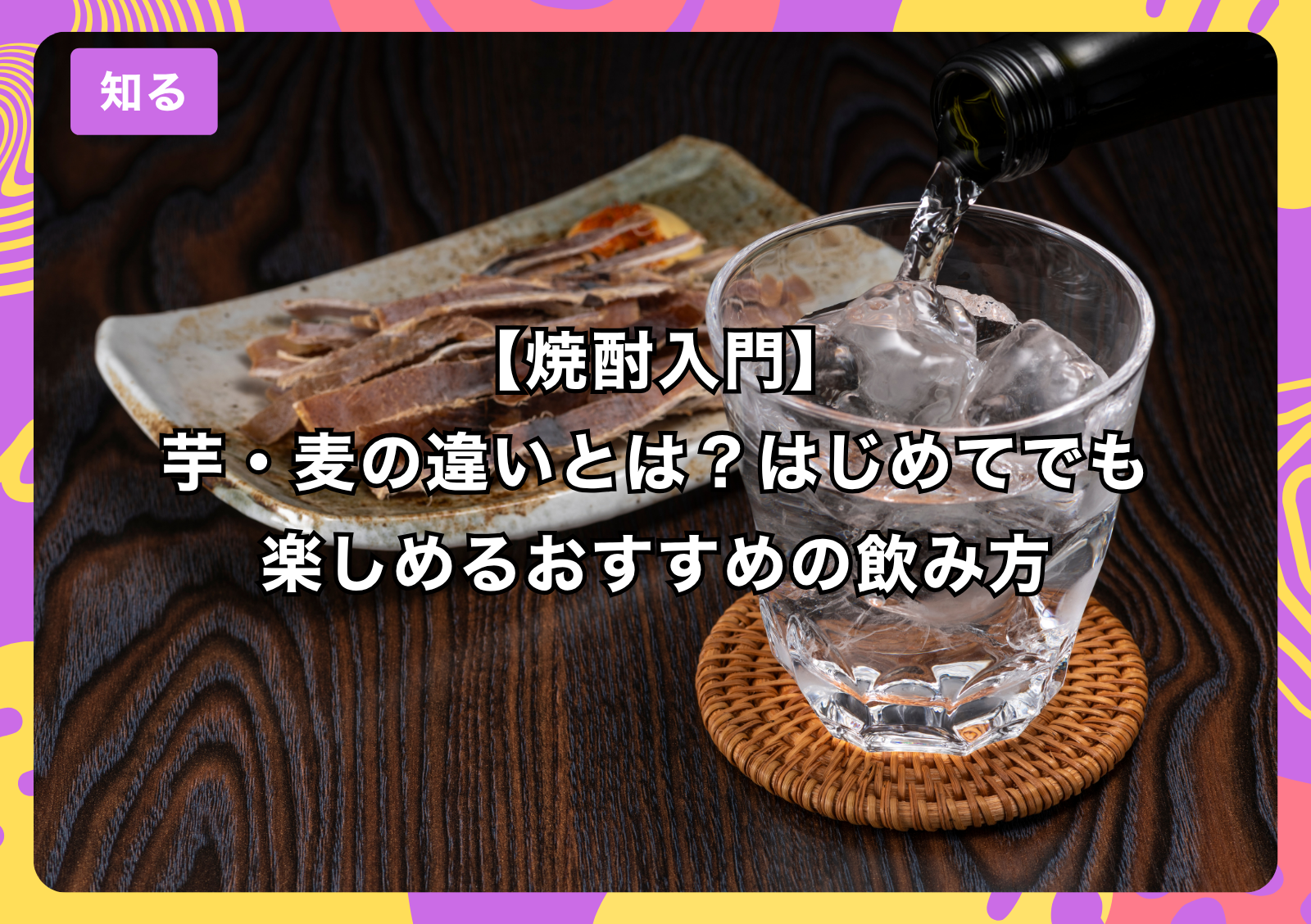
「焼酎ってちょっとクセがあるイメージ」
「芋と麦、どう選んだらいいの?」
「そもそも、どうやって飲むのが正解?」
そんな風に思っている方も多いのではないでしょうか。
焼酎というと、クセが強くアルコール度数が高いお酒という印象を持たれがちですが、じつは飲みやすく初心者にもおすすめなお酒です。
この記事では焼酎の基本から、芋焼酎と麦焼酎の違い、飲み方や保存のコツなど徹底解説していきます!
【基本知識】焼酎とは?

焼酎は穀物などの原料を発酵させた「もろみ」を蒸留して造られる、日本の伝統的な蒸留酒です。日本酒と同じように発酵の工程はありますが、焼酎は“蒸留”というひと手間が加わることで、すっきりとクリアな味わいに仕上がります。
蒸留酒には、他にもウイスキーやジン、ウォッカなどがありますが、焼酎は日本で独自に進化してきた蒸留酒です。アルコール度数は20度前後とやや高めながらも、水割りやお湯割り、ソーダ割りなど飲み方の幅がとても広いのが魅力的です。
芋焼酎と麦焼酎の違い
焼酎の種類はたくさんありますが、中でも人気なのが芋焼酎と麦焼酎。名前の通り、原料にさつまいもや麦を使っているのですが、違いは原料だけではありません。
【芋焼酎】濃厚な香りと甘みがある
芋焼酎の原料はさつまいもで、焼いたさつまいもや皮付きのいもを思わせる、土のような香ばしさと、ほんのり甘い香りが特徴です。
味わいは濃厚で、口に含んだ瞬間に香りがふわっと広がり、喉元に熱を感じるようなコクがあります。後味にも余韻が残るので、お酒をしっかり味わいたい派にぴったり。
芋焼酎はその個性的な香りから、クセがあると思われがちですが、最近はフルーティで飲みやすいタイプも増えています。
【麦焼酎】香ばしさと軽やかさがある
麦焼酎の原料は大麦で、焙煎された麦のような香ばしさと、さらっとした軽さが特徴です。
味の主張が強すぎず料理の味を邪魔しないので、食中酒として使いやすいのがポイント。
アルコールのツンとした感じが少なく後味もスッキリしているため、焼酎は飲みにくそうと思っている方にも飲みやすいですよ。
特にソーダ割りにすると、麦の香ばしさがふんわり残るのに、喉越しはスッキリとしてクセになります。
焼酎のおすすめの飲み方

焼酎はさまざまな飲み方で楽しめて、どんな料理にも合うのが特徴です。ここではおすすめの飲み方をご紹介します。
ストレート・ロック
焼酎そのものの風味をしっかり味わいたいなら、ストレートやロックでいただくのがおすすめです。とくに本格焼酎や長期熟成されたもの、あるいは樽で寝かせて香りをつけた焼酎甲類などは、その個性が際立ちます。
クセが強めの焼酎でも、氷をひとつ加えるだけで角が取れて飲みやすくなることも。古酒などは、小ぶりのリキュールグラスでゆっくり楽しむのもいいですね。
水割り
焼酎の味わいをやさしく引き出し、食事と一緒に楽しみたいときにおすすめなのが水割りです。水で割ることで口当たりが柔らかくなるため、アルコール度数が高めの焼酎でも気軽に楽しめますよ。焼酎ビギナーや、普段お酒に強くない方にもやさしい飲み方です。
お湯割り
本格焼酎の香りをじっくり堪能したい方にぴったりなのが「お湯割り」。お湯と焼酎の黄金比は人それぞれなので、いくつかの割合を試して、自分好みのバランスを見つけてみましょう。
ポイントは、お湯を先にグラスに注いでから焼酎を加えること。そうすることで、まろやかに混ざり、香りもふんわりと立ち上がります。お湯が熱すぎるとアルコール感が強く出てしまうため、60〜70℃程度がおすすめです。
もしアルコールの香りが気になるときは、梅干しや生姜、すだち、レモンなどをひと足しすると、ぐっと飲みやすくなります。
ソーダ割り・ジュース割り・お茶割り
炭酸やジュース、お茶などで割るのも焼酎の楽しみ方のひとつ。クセの少ない焼酎は、割り材の味を引き立ててくれるので、柑橘果汁を加えても美味しく飲めますよ。
一方で、芋や麦など原料の風味がしっかり感じられる焼酎の場合は、その風味とマッチする割り材を使うのがおすすめ。麦焼酎×ウーロン茶や芋焼酎×トマトジュースなど、意外な組み合わせがハマることもあります。
前割り(まえわり)
焼酎の本場・鹿児島で親しまれている前割りは、飲む前日に水で割って寝かせておくという、ひと手間かけた楽しみ方。常温でじっくりなじませることで、アルコールの角が取れ、まろやかで奥深い味わいに変化します。
焼酎の原料ごとの違いについて

焼酎といえば芋と麦が定番ですが、じつはそれ以外にもさまざまな原料が使われています。
それぞれ味や香り、飲み方の相性も違っており、焼酎の世界もぐっと広がります。
米焼酎
米焼酎はその名の通り、お米と米麹から造られる焼酎です。お米ならではのまろやかな甘みや旨味、そしてふわっと香るフルーティーな香りが特徴です。
使用するお米の品種や精米の度合いによって風味に違いは出ますが、どれもどこか懐かしくてホッとする味わいがあります。日本人にとってはとてもなじみ深く、初めて焼酎を飲む方でも親しみやすいお酒といえるでしょう。
料理との相性も抜群で、刺身や焼き魚、肉味噌などの和食はもちろん、シンプルな野菜料理や冷奴などのさっぱり系ともよく合います。
黒糖焼酎
黒糖焼酎は、サトウキビから作られる黒糖を原料にした焼酎です。黒糖ならではのやさしい甘みとすっきりした後味が特徴です。さらに、糖質ゼロ・プリン体ゼロというヘルシーさでも注目を集めています。
「奄美黒糖焼酎」と呼ばれる、鹿児島県・奄美群島だけで造られる特産品もあり、南国ならではの自然と風土が、黒糖焼酎の豊かな香りと飲みやすさを造っています。
そば焼酎
そばは、近年ではスーパーフードとしても注目を集めていますが、焼酎の原料としても密かに人気があります。
主な産地は、宮崎県の高千穂地方や、そばの名所として知られる長野県・北海道など。
芋や麦、米焼酎と比べると銘柄数は少ないものの、そばならではのやさしい香りと、クセの少ない飲み口で、幅広い層に親しまれている焼酎です。
焼酎の賞味期限や保存方法について
焼酎には基本的に賞味期限がありません。アルコール度数が高いため、雑菌が繁殖しにくく、腐ることがないからです。ちなみに焼酎瓶に書かれている日付は、製造日や瓶詰め日であり、賞味期限ではありません。
ただし、保存状態によっては風味が落ちることもあるため、保管には注意が必要です。
開封前は冷暗所に保存
未開封の焼酎は、直射日光や高温多湿、匂い移りの心配がない場所で保管しましょう。押し入れや床下収納など、温度変化が少ない冷暗所がおすすめです。箱入りなら、そのまま箱に入れて保存をしておくといいでしょう。
開封後は早めに飲みきること
一度開けた焼酎は空気に触れることで酸化が進みます。香りや味わいをキープするためにも、早めに飲み切るのが理想的です。
保管時はキャップをしっかり締め、日光や照明の当たらない場所に置きましょう。
冷蔵庫保存はNG?
焼酎は冷やしすぎると旨み成分が沈殿することがあります。長期保存には向かないため、冷蔵庫に入れるのは一時的にとどめておき、基本は常温で保存しましょう。
まとめ
焼酎は、芋・麦・米・黒糖・そばなど原料によって風味が大きく変わるのが特徴です。とくに芋焼酎はコクが深く、麦焼酎はすっきりとしてまろやか。ご自身のお好みやシーンに合わせて選ぶのもおすすめ。
飲み方も、ロックや水割り、ソーダ割りなどなどバリエーション豊富です。ぜひ気になる焼酎を探して香りや味を楽しんでくださいね。
